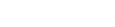ゲームや動画はいいの?悪いの? 上手に付き合えばいいこともいっぱい!

10.16 2019
こんにちは!ていねい通販の下辺です。
今年の秋は台風の影響などもあり、いつもより雨が多い気がしました。外に出かけられない我が家の子どもたちは、いつも以上に大好きなゲーム&動画三昧。
「外は雨だから仕方ないか…」なんて黙って見ていたのですが、おやつの時間さえ忘れて夢中になっている姿に親ながらビックリ!
ゲームを禁止にしているご家庭もある中で、うちってこのままでいいのかしら?
ゲームで集中力や問題解決能力が高まる!?
ママ&パパ世代も、子どもの頃は夢中になった思い出があるゲーム。さらに時代が変わった今、ゲームに加えて無料の動画サイトにハマる子どもたちも増えてきました。
パソコンやゲーム機がない家庭でも、スマホがあればどちらも楽しめるもの。目が悪くならないか?勉強をしなくならないか?…など、心配になるママも多いですよね。
よく驚かされるのは、まだまだ小さな子どもがママのスマホをさわって、自分のやりたいアプリや動画を器用に検索すること。
特にやり方を教えたわけではないのに、“興味”が自主的に学ぶ力になっているのです。
特にゲームに関するルールを決めている家庭では、プレーを始める前に集中して宿題を終わらせたり、上手に一日のスケジュールを組みたてる子どもが多いというデータも。
もちろんやりすぎは禁物ですが、このようにゲームや動画を通して得るもの、学ぶものもたくさんあるんですね。

また、昔に比べて現代では単純な操作だけでクリアできるゲームは少なくなっています。
その複雑なストーリーやシステムの理解を通して期待できるのが、創造力や判断力、問題解決能力の成長。好きだからこそ、前向きに学ぼうとする…。今やゲームは楽しめる教材なのです。
ゲームを通して得られるメリット
■ルールを守る意識と時間管理能力が身につく
ゲームが好きな子どもは、「1日〇時間まで」「〇〇を終わらせてから」というルールをしっかり守ります。
遊べる条件を満たすまでに、やるべきことをこなす自主性や集中力、時間管理能力は、成長してからの勉強にも活かされます。
■鋭い判断力や問題解決能力が磨かれる
ストーリーやシステムを読み解きながら、「その場の状況に応じて何をすべきか?」という判断が求められるゲーム。
自らの考えと判断で見事に問題を解決できた喜びが、考える力を育みます。
■漢字や英語、地理、歴史に関する知識が増える
ボイス付きのゲームが増えている今、難しい漢字や英語を“字幕+音声”で学べるのもゲームのメリット。
またリアルなストーリーを通して、国内外の地理や歴史に関する知識も楽しみながら学べます。
乳幼児にオススメ!学べる動画や知育アプリ
公共施設で長く待たされる時や高速道路の渋滞時など、じっとすることが苦手な乳幼児はすぐぐずりがち。だからといって、すぐにスマホやタブレットを渡してしまうのもなんだか気が引けますよね。
特に無料の動画サイトにはさまざまな内容の動画があるため、そこから悪影響を受けてしまうことを心配するママも多いのでは?
でももし、その時間を“学び”につなげられると、ママの心配も解消できるかもしれません。
例えば、無料の動画サイトでは【知育・教育】に関するチャンネルがあり、ひらがなや数字、英語を学べる動画から、動物や植物、乗り物の名前などを覚えられる動画まで、子どもの成長に役立つものが数多くあります。
声が出せる状況であれば、童謡や手遊びの動画を見ながら親子で一緒に歌うのも楽しいものです。

一方、動画サイトはNGというご家庭であれば、あらかじめ乳幼児向けのアプリをダウンロードしておくのもオススメ。
色や形をクイズ形式で覚えられる低年齢向けのアプリから、小学校入試の受験対策となる本格的な入試問題集アプリまで、目的に応じて選びましょう。
いずれを利用するにしても、子どもに自由にスマホを触らせるのではなく、まずママが「何を見せてもいいのか?」という判断を下すことが肝心。
また公共の場で楽しむのであれば、マナーモードやイヤホンを利用するなど、周りの人に対する配慮を覚えさせることも大事ですね。
普段では見られないものが子どもの世界を広げる
ここまでゲームや動画のメリットを紹介しましたが、その両方を禁止しているご家庭も多いかもしれません。もちろん、遊び方や使い方によってはたくさんのデメリットもあります。
ただし、ゲームや動画そのものが悪影響だと決めつけず、遊ばせる環境・見せる内容に問題がないのかを考えることも必要。
ママやパパの工夫や管理によって、それらは学ぶ道具にも、成長を妨げる道具にも変わるんです。
ゲームや動画の大きな魅力のひとつは、身近な毎日では触れられない世界を体感できること。

何千年前の海外の国、険しい大氷原やサバンナの大平原、今はまだ夢物語の宇宙での暮らし。さまざまな疑似体験が、子どもの夢や興味を広げてくれるでしょう。
「ねえ、ママ。僕ね、おっきくなったらお月さまで働く人になりたいの」
「へ~、素敵な夢だね。でも宇宙に行くなら体を強くしないとね。あと、宇宙人と話せる言葉を覚えないといけないかも…」
「ホントに? でもさぁ、僕まだ小さいから今から頑張ればだいじょうぶだよ。スイミングも行ってるし、英語のお勉強だってするもん」
「すごいね!それだけ頑張ったらきっと夢も叶うね。たっくんが月に行ったら、何をおみやげに買ってきてもらおっかな?」
「んとね~、おだんごでしょ。たこ焼きでしょ。あとはぁ…、スイカかな?」
「…なるほど。お月さまで売ってるのはみんな丸いのね(笑)」
子どもの育て方も、ゲームや動画との付き合い方も、本当に正しい答えは見えないもの。
「よその家はこうだから」で決めるのではなく、子どもの性格や生活環境などとのバランスを考えながら、我が家なりの正解を導き出すほかはありません。
…あら、じゃあ私もゲームで判断力を鍛えた方がいいのかも⁉