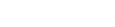物資だけでなく、気持ちにもしっかり準備を。わが家の「防災対策」は大丈夫?

01.25 2019
こんにちは!ていねい通販の藤本です。
新年を迎えて、早くもひと月。みなさんは平成最後のお正月を楽しく過ごせましたか? わが家は今年も、パパの実家に親族一同が大集結。
うちの子どもたちだけでなく、甥や姪にもヤンチャ盛りが多いため、お正月というよりまるでお祭りのような賑やかさでした(汗)。
それ以上にドタバタだったのが年末の大掃除。ついでだからと、以前の『ていねい通信』で紹介した【お片付け術】を参考に、お家全体の整理整頓にチャレンジしたんです。
するといろんな場所から意外なモノが出てくる、出てくる…。一年前に新調した防災グッズが押入れの奥深くに眠っているのを発見した時は、わが家の危機管理の甘さを痛感しちゃいました。
今回の反省をもとに、日頃の防災対策をしっかり見直してみようと決意。もちろん普段から防災に力を入れているご家庭も多いと思いますが、安全への備えは何度チェックしてもムダにはなりません。
いま一度、気を引き締めるためにも、今日からできる防災対策を学んでいきましょう。
まずは家庭の防災ルールづくりから
高いところにモノを置かないようにしたり、倒れやすい家具を固定したりと、小さなお子さんがいるご家庭は特に、防災対策に気を遣っているのではないでしょうか?

このように日頃から準備を進めておくことはとっても大事です。ただ、しっかりと準備を進めた…という安心感から、気持ちに余裕が生まれてしまうのも事実。大事なのは“備えを継続する”ことなんです。
そこで役立つのは家庭内のルールづくり。誰かひとりが防災対策を進めるのではなく、わが家でどんな用意をしているのかを家族全員で共有したうえで、緊急時の行動についても決めておきましょう。
☆今すぐできる家庭内のルールづくり
①避難物資の消費期限チェック
飲料水や非常用トイレなど、ケース単位で備蓄しているモノは、消費期限や内容物の劣化を見落としがち。
定期的に箱を開いて中身の状態を確かめる習慣をつくろう。
②ガソリン&充電は常に満タンに
緊急時の避難場所にもなる車は、常にガソリン満タンが理想。
最低でも、残量が半分を切ったら給油、毎週末には必ず給油など、家庭内のルールを決めておこう。
日頃から携帯電話やモバイルバッテリーのフル充電もお忘れなく。
③持ち出すモノの中身や置き場所を共有
非常持出袋は靴箱の上に置く、ハザードマップを玄関ドアに貼りつける、など、
緊急時に持ち出すモノや、その保管場所を家族と共有。
違う場所に置かれていることに気づいた時は、必ず元の位置へ。
④災害発生時の行動の優先順位は?
火を消す、懐中電灯を確保する、周辺に割れたガラスがないか確かめる、など、
災害発生時にまず誰が何をするかを、決めておくことも大切!
ご近所さんは非常時の強い味方
普段から家庭内で防災意識を高めていても、やはり非常時はご近所さんとの協力関係は大切。避難時の声掛けや避難場所での情報交換を行える人が数多くいるのはとても心強いものです。

特に家族構成や子どもの年齢、アレルギーの有無、飼っているペットの種類など、共通点が多ければ多いほど、避難場所で必要となるモノが似てくるため、万が一持ち出せないモノがあってもお互いにサポートしあうことが可能。
一方、共通点が少ない家族の場合は、必要なモノとそうでないモノが異なってくるので、物々交換が行いやすくなります。
そんな意味でも、常日頃からさまざまなご近所さんと信頼関係を築いておくのは大切なこと。顔なじみのママ友さん以外にも、日々のあいさつや世間話を通じて、少しずつ絆を深めたいものですね。
いざという時に行動できる心を育てよう
どれだけ物資面の準備を進めていても、急に大きな災害に見舞われると誰もがパニックに陥ってしまうもの。いざという時に、正しく、素早く行動するためには“気持ち”の準備が欠かせません。
近年では地域の自治会レベルでもさまざまな防災活動に力を入れており、定期的な避難訓練も開催されています。

こうした場に積極的に参加することはもちろん、家庭内でも避難経路の確認を繰り返し行うなど、家族全員で緊急時の心構えを育てておきたいものです。
「あれ、今日も公園まで遠回りするの?」
「そうだよ、なんでいつもこの道を通るかわかるかな?」
「知ってるよ。大きな地震が来た時にみんなで逃げる道。その時はヘルメットと銀色のリュックもいるんだよ」
「正解! たっくんはいつも頼りになるね~」
「エヘヘ。だから、もしママが道を忘れても大丈夫だよ。僕が連れて行ってあげるから」
小さな心掛けの積み重ねが、いざという時に家族を助ける…。まさに「備えあれば、憂いなし」です!